高圧進相コンデンサと電流メーター
とある工場の受電設備。ここには高圧進相コンデンサがついている。
祝日で負荷は停止状態。
なのに高圧電流メーターは7Aを表示している。
なぜ高圧電流メーターに電流が流れているのか?
そしてこの状態は、電力を消費している状態なのか?
電流メーターで電流が表示される原因とは?
変圧器の無負荷損分変圧器の無負荷損はせいぜい数100Wなのでそんなに流れない。
変圧器のカタログに概算値が載っている。
進み無効電力
75kvar程度のコンデンサが常時入りであればそのくらいの電流は流れる。
この時に流れている電流は主に進み無効電力である。
電力消費には影響しない。
有効電力分
有効電力も多少は消費している。
途中の配線でのロス、コンデンサ自体のロスなど。
サーモグラフィーで見るとコンデンサも熱を持つことがわかる。
発熱するということは有効電力の損失がある。
進相コンデンサの消費電力
理想値として、損失率tanδ=0.025%以下を目標として製作しているらしい。定格容量106Kvarの場合
106 × 1000 × 0.025 × 0.01 = 26.5(W)
ただし製造時の目標値なので、経年劣化したコンデンサはもう少し大きくなるらしい。
低圧側にコンデンサがある場合、変圧器の負荷損にも関わってくる。
コンデンサの損失係数 tanδとは?
コンデンサ内部で消費されるエネルギーを表す特性の一つ。所定周波数の正弦波電圧で生じる「電力損失 ÷ 無効電力」
誘電損失とも呼ばれる。
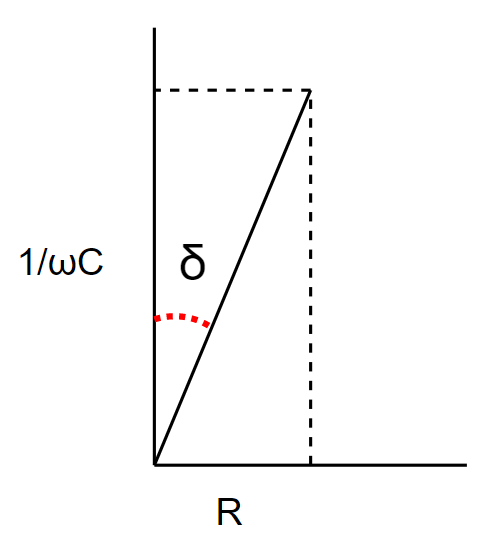
理想的なコンデサは、印加電圧に対して電流の位相は90度進む。
理論的にはコンデンサ内での電力はゼロで損失がない。
しかし実際のコンデンサには、
・等価直列抵抗(ESR)
・等価直列インダクタンス(ESL)
・絶縁抵抗(IR)
ESR(誘電体の誘電損失、電極やリード線などの影響)
ESL(電極やリード線などの影響)
が存在する。
誘電体に加えた電界が時間的に変化した場合、誘電体の抵抗成分(ESR)によって電束密度変化が遅れる。
この遅れによって電流の位相は δ だけ遅れる。
電圧と電流の位相差が90度ではなくなる。
そこでコンデンサ内での電力損失が発生する。